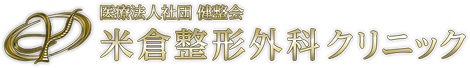2025/10/25
こんにちは!
米倉整形外科クリニックのリハビリ担当です。
私たちは「わかりやすく」「ていねいに」「あたたかく」を心がけながら、皆さんの痛みと向き合っています。
今日は、ちょっと意外に思われるかもしれませんが、「脚の痛みについて足の裏からアプローチした」実際の事例をご紹介します。
私たちが日々の臨床で参考にしている書籍のひとつが、『園部俊晴の臨床「膝関節」』です。
理学療法士や整形外科分野の臨床家を対象とした専門書であり、著者・園部俊晴氏が長年の経験から導いた
「痛みの本質を見抜くための臨床推論」が体系的にまとめられています。
本書では膝を構成する主要な9つの組織(半月板・靱帯・関節包・脂肪体など)ごとに
評価と治療のアプローチが詳細に解説されています。
中でも特筆すべきは、「症状から原因を推論するプロセス」を重視している点です。
今回はこの考え方を基に、当院スタッフが体験した「脚の痛み」に対するアプローチをご紹介します。
1.痛みの原因は「膝だけ」とは限らない
研修当日は「歩くときに左膝の内側が痛む」事象について取り上げました
詳しく調べてみると膝の内側の少し下(鵞足部:がそくぶ)という場所に痛みがありました。
そこには3つの筋肉(縫工筋・薄筋・半腱様筋)が集まっています。
検査をすると、そのうちの縫工筋(ほうこうきん)という筋肉が硬くなっており、伸び縮みがスムーズにできていないことがわかりました。
2.なぜ縫工筋に負担がかかったのか?
歩く姿を観察すると、痛みのある膝は少し外にねじれた状態でした。
縫工筋は「脚を内側にねじる」働きがあるため、外にねじれたままだと常に引っ張られたような状態になります。
さらによく見てみると、歩くときにかかとが内側に入り込む動きがありました。
これは足首の骨(距骨:きょこつ)が外向きになっていることが関係しており、足元の小さな動きが膝の痛みを引き起こしていたのです。
3.治療のポイントは「足の裏」でした
そこで、膝ではなく足の裏の筋肉(長母趾屈筋:ちょうぼしくっきん)をストレッチしました。
この筋肉は親指を動かすときに使う筋肉ですが、実は膝とも深く関係しています。
ストレッチを行うと、縫工筋の動きもなめらかになり、膝の痛みがなくなりました。
痛みが消えるまでにかかった時間は、ほんの数分ほど。
スタッフ自身も「こんなところが原因だったなんて!」と驚いていました。
4.体はつながっています
今回の経験から改めて感じたのは、「痛い場所=悪い場所」ではないということです。
人の体はたくさんの筋肉や関節が連動して動いているため、どこか一部の動きが悪くなると、別の場所に痛みが出ることがあります。
「膝が痛いから膝を揉む」「痛いところを伸ばす」だけでは、根本的な解決につながらないこともあります。
5.膝の痛みでお困りの方へ
・痛み止めを飲んでも良くならない
・マッサージを受けてもすぐに戻ってしまう
・歩くたびに膝が気になる
そんな方は、もしかすると体の別の部分に原因があるかもしれません。
当院では、理学療法士が一人ひとりの体の動きを丁寧に観察し、痛みの原因を見つけ出していきます。
一緒に、痛みのない毎日を取り戻していきましょう!